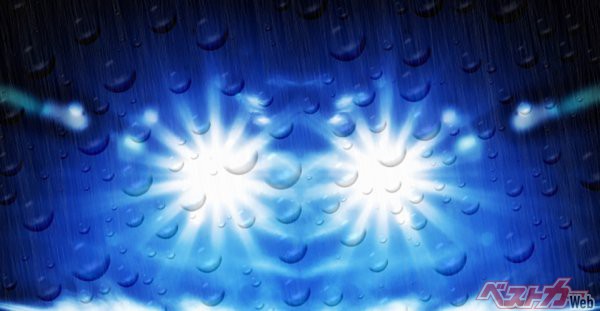交差点の右左折をする直前に曲がる方向の逆にハンドル操作をして膨らんでから曲がる「あおりハンドル」、車間距離を詰めて速く進むよう催促する「あおり運転」などの運転行為は今でもよく見かける光景です。
今回は、あおりハンドルやあおり運転がなぜ危険なのか、元自動車教習所の教官で国家資格を保有する筆者が解説します。
文/齊藤優太、写真/Photo AC、AdobeStock(トップ画像=Imaging L@AdobeStock)
【画像ギャラリー】心当たりのある人はすぐに直そう!! 周囲に迷惑と危険を撒き散らす「3つの危ない運転行為」(4枚)画像ギャラリー
■危ない運転行動その1:あおりハンドル
あおりハンドルは、交差点の右左折をする直前に曲がる方向とは逆にハンドル操作をして、あえて大回りをして右左折する行為です。よく見かけるあおりハンドルは、後続車や対向車など周囲の交通の妨げになる運転行為であるため危険なのです。
筆者が実際に教習所で指導していた時にも、あおりハンドルをする生徒がいました。筆者があおりハンドルについて指摘すると「自分は、あおりハンドルなんてしてない」や「なんでダメなんですか?」と言われたため、あおりハンドルの危険性について次のように説明しました。
「あおりハンドル(右左折直前の逆振り)をすると後続車が驚き、急操作(急ハンドルや急ブレーキ)をさせてしまったり、通行できなくなったりすることがあります。
また、逆振りは対向車線側の通行を妨げてしまう可能性もあることから危険なのです。さらに、左折時に車体を右側に振ると、二輪車が入るスペースができてしまい、巻き込み事故を起こすリスクが高くなります」。
このような危険性があることからあおりハンドル(逆振り)は危ないのです。
法律では、交差点の右左折の方法について、「左折する時は、あらかじめ道路の左に寄って道路の左端に沿って徐行して通行する」、「右折時はあらかじめ道路の中央に寄り、交差点の中心のすぐ内側を徐行して通行する」と定められています。
あおりハンドルは、ほかの交通の通行の妨げになったり、法律に反した右左折方法であったりするため、やらないようにしましょう。
ただし、生活道路やあまりにも狭い路地へ進入する時は、あらかじめ道路の端に寄って右左折するのが難しいこともあります。積極的に推奨することはできませんが、車幅1台分ギリギリの道や狭い道などに入る時は、周囲の安全をしっかりと確認した上で最小限の逆振りで曲がるようにしましょう。
■危ない運転行動その2:近すぎる車間距離
近すぎる車間距離は、車間を必要以上に詰めて走行することで、あおり運転の典型例とも言える危険な運転行為です。
車間距離が近すぎることによる危険は、追突するリスクが高くなることにあります。車間距離を詰めて走行し、何らかの事情により追突を避けようとした場合、急ブレーキや急ハンドルなどの急操作をしなければなりません。
急操作をすると自分自身が危険にさらされるだけでなく、ほかのクルマやバイクなどを巻き込んだ多重事故に発展する危険性もあります。そのため、車間距離を詰めすぎて走行するのは危険なのです。
車間距離について法律では、前の車両が急停止しても追突しない距離を保つよう定められています。言い換えると、停止距離(空走距離+制動距離)以上の車間距離を空ける必要があるのです。
筆者が実際に運転指導やペーパードライバー講習をしていると、「車間距離って、どのくらい空けておけばいいですか?」という質問をよくされます。その時に筆者は、「自分自身が安全だと思う間隔を空けてください。詰めすぎると違反ですが、空きすぎている分には、違反ではありません。
交通の流れを乱さず、少し車間距離を空けすぎてるかもしれないと思う間隔がちょうどいいでしょう」と答えています。
車間距離は、詰めすぎると「車間距離不保持」という違反です。また、あおり運転(妨害運転)の対象となる10類型の違反のひとつとなっています。
車間距離を長めにとっておけば、前車が急ブレーキをかけたり、前方の危険の発見が少し遅れたりしても、急操作で回避する必要がなくなります。そのため、「少し間隔を空けすぎているかもしれない」と感じるくらいの車間距離がちょうどよいでしょう。
■危ない運転行動その3:周囲にクルマやバイクなどがいるのにハイビームのまま走り続ける
カーシェアやレンタカー、カーリースなど、さまざまな方法でクルマに乗ることができるようになった現代では、ハイビームのまま走り続けているクルマを目にすることが増えました。
また、オートライトが義務化されたり、オートハイビーム機能を装備しているクルマがあったりするものの、いまだにハイビームで走り続けるドライバーを目にします。
ハイビームにしているクルマのドライバーは、見える範囲が広くなるため運転がしやすくなります。しかし、対向車やハイビームのクルマの前にいる車両の運転者は、非常に眩しいです。
眩しい状態を受け続けると前方の交通状況の認識が遅れたり、何らかのトラブルが起きた時に急操作を強いられたり、事故になったりすることがあります。
また、周囲にクルマやバイクなどがいるのにもかかわらず、ハイビームで走り続けるのは「減光等義務違反」です。さらに、あおり運転(妨害運転)の対象となる10類型の違反のひとつとなっています。
教習所の学科教習で「原則として走行用のヘッドライトがハイビーム、すれ違いをする時にヘッドライトをロービームにする」と教えられたことを覚えている方も多いでしょう。確かに、法律の条文をわかりやすく言い換えると、教習所で教えていることと同意になります。
しかし、実際の道路では、対向車や先行車などが多い市街地を走行する場面も少なくありません。人によっては、市街地やクルマ、バイクが多い場面でしか走らないという方もいるでしょう。
そのため、ロービームがメインとなり、必要に応じてハイビームを活用するという使い方になってしまうのはしかたないことなのです。
ハイビームで走り続けると、自分にとって好都合なことが多いものの、周囲のクルマやバイクなどは非常に眩しく、運転の妨げになります。運転中は、メーター内のハイビームのマークが点灯し続けていないか(オートハイビーム機能のクルマを除く)、時々確認しながら走行するようにしましょう。
■まとめ:クセになってしまった運転行為は意識しないと直らない
今回紹介してきた「あおりハンドル」、「車間距離の詰めすぎ」、「ハイビームで走り続ける」などは、どれも危険な運転であり、クセになっている行為です。また、自分で問題ないと思っていても、周囲のクルマやバイクなどの運転者は「あおられている」と感じることもあります。
このようにクセになっている運転行為は、客観的な視点で運転をチェックしてもらい、指摘されたことを意識しないと直りません。運転に慣れているから大丈夫だと過信せず、定期的に運転チェックをしてもらい、より安全な運転ができるよう自己研鑽していくことが大切だといえるでしょう。
【画像ギャラリー】心当たりのある人はすぐに直そう!! 周囲に迷惑と危険を撒き散らす「3つの危ない運転行為」(4枚)画像ギャラリー
投稿 後続ドライバーは思わずヒヤリ!? なぜ「あおりハンドル」は危険な運転なのか? 危ない運転3選 は 自動車情報誌「ベストカー」 に最初に表示されました。